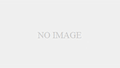今回は荼毘に付すということばについてご説明いたします。
有名な方、著名人の訃報を聞くと、
「~日に荼毘に付されました。」というニュースも耳にします。
この荼毘に付す、荼毘に付されるという言葉の
意味や由来、英語表現について解説します。
荼毘に付すとは
荼毘(だび)に付(ふ)すとは、亡くなった人を火葬することです。
「荼毘」というのは火葬のことです。
火葬のために死体を焼くことをパーリ語で「燃やす」という意味のジャーペーティjhāpeti,サンスクリット語でディヤーパヤティdhyāpayatiと呼び,「荼毘」はこれらの言葉から音をとったものと考えられています。
インドでは古くから四葬(水葬,火葬,土葬,風葬)の風習がありましたが,その中でも火葬が最も正式な埋葬のスタイルとされていました。
日本に火葬の習慣が伝わったのは700年ごろ。
僧侶や天皇から始まり、次第に仏教徒の貴族から民衆に広まりました。
厳密には、仏教徒がなくなったときに火葬にすることを
「荼毘に付す」といいます。
ご遺体を火葬にすることそのものと、
その前後に行われる葬儀全体も指す言葉です。
荼毘に付されるの意味
荼毘に付されるという言葉は、『亡くなった方が火葬される』という意味です。
日本には古来から、死や病気に関する直接的な言い方を避ける風習があり、
「(ご遺体を)燃やします」
「火葬します」
という直接的な言い方よりも
「荼毘に付す」
という言い方の方が好まれていました。
故人の死を悼んで言う言葉です。
荼毘に付すの英語表現
火葬は英語でcremation。
彼のご遺体は荼毘に付された。
His body was cremated.
お葬式をする
to hold a funeral
私たちは今日、彼を火葬する。
We will cremate him today.
(火葬した)遺骨を捨う
gather ~’s ashes
昨日彼の葬儀が終わった。
His funeral ended yesterday.
などの例文があります。
火葬のスタイル
日本で行われる火葬は、遺体を火で焼いて、残った骨を壺[つぼ]に入れ
お墓や納骨堂に納めます。
日本火葬率は99%で世界一ですが、世界の中では土葬が主流です。
日本の火葬は欧米の方法とは異なり、遺骨の形が残るよう調節されています。
火葬後に骨を拾い骨壷または骨箱に納めることを拾骨(収骨、骨上げ)と言います。
火葬以外の葬送スタイル
火葬以外の埋葬方式には以下のようなものがあります。
・埋葬(土葬・墓葬)
・宇宙葬
・海洋葬
・水葬
・鳥葬
・樹木葬
・風葬
・冷凍葬
まとめ
荼毘に付す、荼毘に付されるという言葉について解説を行いました。
古風な言い方ですが、「火葬にする」という言い方よりも、
亡くなられた方を尊ぶ意識の伝わる表現です。